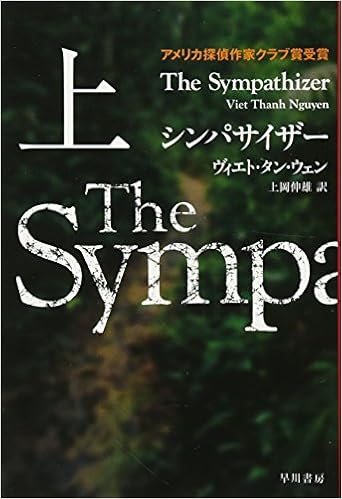ハヤカワ文庫
ヴェトナム戦争を扱った小説は数多いが、そのほとんどは欧米人が書いたものだ。本作品は、ボートピープルとしてアメリカへ亡命したヴェトナム系アメリカ人作家から見た、ヴェトナム戦争や亡命ヴェトナム人社会の実態を描いたユニークなスパイ小説である。
主人公は、「将軍」と呼ばれているヴェトナム共和国(南ヴェトナム)・秘密警察長官の右腕とし働く大尉。1975年の陥落寸前のサイゴンから将軍の家族とともにアメリカへ亡命し、再起を目論む将軍の手足となって働いている。しかし、主人公の裏の顔は将軍の動向を監視する北ヴェトナムのスパイだった。
作品には亡命ヴェトナム人作家でしか書き得ない場面がいくつかある。例えば、ヴェトナム戦争を描いた大作映画(F・コッポラ監督の「地獄の黙示録」がモデル)の制作現場。制作スタッフの一人として参加した主人公は、同胞が正しく描かれるよう監督に進言するが、「誰もそんなことにクソほどの関心も払わない」と一蹴される。ハリウッドの白人至上主義や自分たちの価値観を押し付けようとするアメリカの傲慢さを見て取ることができる。
もう一つの例は、亡命した元軍人たちの不満だ。彼らは配達夫や用務員など、アメリカ社会の底辺の住人として暮らしている。誇り高き軍人たちは、そのことに我慢ならない。「戦争は地獄かもしれないが、このクソ溜めよりはましだ」と息巻く彼らの夢は、ヴェトナム共和国の再興である。そんな彼らにとって、同胞でありながら、アメリカの物質主義を享受する〝大食漢の少佐〟は堕落した裏切り者であり、彼らの夢を「時代錯誤」と批判する新聞記者は許しがたい存在だった。将軍は主人公に、この二人の暗殺命じる。スリリングな暗殺場面は、この小説がスパイ小説であることを、あらためて思い出させてくれる。
主人公はフランス人宣教師が現地の娘に産ませた欧亜混血の私生児である。この設定がスパイである主人公を象徴している。西洋と東洋、資本主義と共産主義など、相対する二つ世界を複眼的な視線で見つめ、それぞれにシンパシーを感じている。物語の後半、主人公は北ヴェトナムの再生キャンプに入れられる。そこで彼が見たのは、独立と自由を求めて戦った革命家たちが勝利した後、今度は彼らが他の者たちの独立と自由を奪っている現実だった。「Nothing is more precious than independence and freedom.(独立と自由以上に大切なものは何もない)」というのは、かつて主人公がシンパシーを抱いたホーチミンのスローガン。複眼視点を持つ主人公はこれを「独立と自由のために戦った革命が、いかにこうしたものの価値を〝何もない〟以下に下げてしまったか」(訳者)と読むのだった。
2015に発表された本作品はアメリカでベストセラーとなり、ピュリッツァー賞、アメリカ探偵作家クラブ賞をはじめとする八つの文学賞を受賞した。