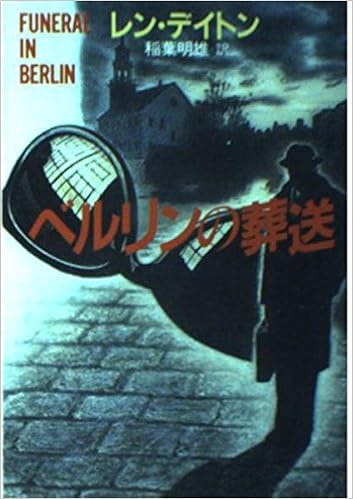ハヤカワ文庫
イギリス内閣直属の諜報機関WOOC(P)に所属する「わたし」は、酵素学に関する世界的な権威であるソビエトのセミッツァを西側に亡命させるため、ベルリンへ飛ぶ。現地連絡員のヴァルカンや西ドイツの諜報機関の協力を得て、セミッツァを別人に仕立てて霊柩車の棺に潜ませ、ベルリンの壁を越境する手筈になっていたのだが……。
イアン・フレミング、ジョン・ル・カレ、グレアム・グリーンなどイギリスのスパイ小説作家は伝統的にパブリックスクールを卒業した上流階級に属する人たちであり、彼ら自身も将校や官僚として、諜報の仕事に携わった経歴を持つ。それに対して、運転手の息子として生まれたレン・デイトンは、グラマースクール卒業の労働者階級出身である。様々な職業を経たのち空軍に入隊。勿論、将校としてではなく、兵卒である。兵営で暮らした相手は賭付業者(のみや)の走り使い、サーカス芸人など、〝人生の縮図を見るような種々雑多な連中〟(訳者あとがき)であったという。そうした経歴が、それまでの上流階級出身のスパイ小説作家たちが描くのとは一味違う作品を生み出したといえよう。
主人公はホワイトホール(我が国で言えば、霞が関の官庁街)にあるMI5やMI6にではなく、シャーロット街というロンドン下町の雑居ビルに事務所を構える内閣直轄の諜報機関に勤務。接待費の枠をはみ出すと上司から嫌みを言われ、拳銃は任務の都度、陸軍省に申請書を提出してから携行するなど、デイトンは「エリート階級だったスパイを普通の公務員の現実に引きずりおろした」(直井 明『スパイ小説の背景』論創社)のである。
しかしながら、描き方は普通ではなかった。ハメットやチャンドラーなどのハードボイルド小説の主人公のような相手に媚びないふてぶてしい態度、思わせぶりで意味深な会話、そして、〝スパイ小説の詩人〟と言われるゆえんの凝った表現。例えば、「風が発狂した海鷗(かもめ)のような金切り声をあげてわたしのまわりを吹きまくった」(稲葉明雄訳)、や「指のあいだから銀の砂のような朝がこぼれ落ちる感触を楽しんだ」という比喩表現の何と詩的でキザなことか。これが楽しめなければデイトンのファンになるのは難しいだろう。小林信彦が『地獄の読書録』(1989年 ちくま文庫)の中で、本作品を「プロットそのものより、細部のケンランたる描写や会話で読ませる小説」と評しているが、言い得て妙である。
デイトンはキム・フィルビー事件に材をとった『イプクレス・ファイル』(1962年)でデビューし、三作目である本作品(1964年)の後も精力的に「わたし」を主人公とした作品を発表している。しかし、70年代以降に発表されたものは、どちらかといえば冒険活劇に近い。そういう意味で、最もデイトンらしい味が出ているのが本作品であり、彼の代表作といえよう。