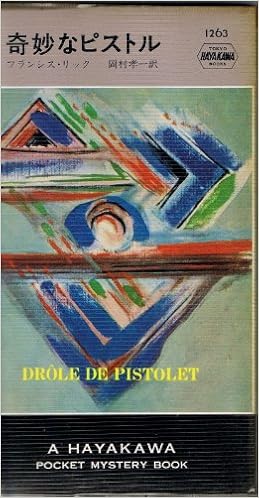ハヤカワ・ポケット・ミステリ
ロンドンに潜入していたKGBのスパイ、ヤコは、隠し場所から連絡文を取り出したところを英国秘密情報部におさえられた。逮捕された彼は同情報部から自分たちに協力すれば、希望する国のパスポートと1万ポンドを与えて自由の身にしてやると言われる。組織に忠誠を誓って口を割らないでいる代償は、この先、死ぬまで牢獄の中で暮らすことだ。ヤコはドーバーに到着するソ連側スパイの逮捕に協力し、約束通り自由の身となった。しかし、時をおかず、ヤコの裏切りに気付いたKGBは、早速、暗殺チームを編成し、彼を追う。
実際のKGBも裏切り者に対しては苛烈だ。キム・フィルビーがソビエトのスパイであることを暴露したKGB元大佐のゴリツィンは、イギリスへ亡命してから5年後の1967年、カナダで偽名を使って暮らしていたところへ、KGBの刺客が送り込まれた。近いところでは、プーチン政権を批判していたKGB元中佐のリトヴィネンコが、2006年、亡命先のロンドンでポロニウムという放射性物質の毒を盛られて暗殺されている。「裏切り者には死をもって償わせる」というのがKGBの不文律なのだ。
本作品では、犬が重要な役目を担っている。KGBの裏をかくため、ヤコはパリ郊外にあるフォンテーヌブローの森から山中へ潜伏した。そこに、偶然、迷い込んできた一匹の毛の長い大型犬。真夜中、何かの気配を察して、かすかに唸り声を発し、ヤコにKGBの刺客の存在を知らせたのだ。それ以来、彼はこの犬に〝トム〟と名付け、連れて歩くようになった。後になり先になり付いてくるトム。風呂に入れてやると、面白くなさそうに湯船につかり、シャワーをかけてやると、蛇口に口をつけるようにして水を飲むなど、犬の描写にリアリティがある。おそらく、作者も実際に犬を飼っていたに違いない。
いくら逃げても執拗に追いかけてくるKGBの刺客。ヤコはある疑念を抱く。もしかして、この犬の体のどこかに発信機が埋め込まれているのではないか? もし、そうであるなら、トムは刺客をヤコのところへ導く誘導役になりかねない。彼はこの犬の処分を決心するが、無邪気な目でヤコを見つめ尻尾をふるトムを見ていると、決心が鈍ってしまう。
1969年のフランス推理小説大賞を受賞した本作品は、ノワール系作家、フランシス・リックの代表作である。彼はこの他にも、看守を殺して逃亡する男を主人公とした『危険な道づれ』(1973年)を発表しているが、敵の影に脅えながら不安で孤独な戦いを強いられる主人公の丹念な内面描写は、本作品にも共通する。
どこに隠れていても、生きている限り、KGBの魔の手から逃れることはできない。それが分かっているヤコは、ミレル(道中の途中から、彼と行動を共にするようになった女性)に危険が及ぶのを防ぐため、ある決心をする。エンディングは、何ともやるせない。